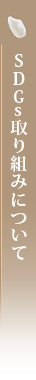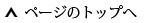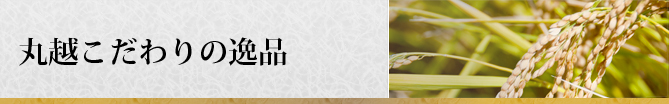
JA能登すずし 石川県珠洲市産 コシヒカリ
JAすずしは、日本列島のほぼ中央、日本海に突き出た能登半島の先端に位置し、恵まれた自然環境と多くの伝統・文化をもちあわせています。稲作を中心とした農業は、気温、降雨、降雪も程よく、全国的にも高い評価を得ています。関西市場においても珠洲ブランドが定着しております。このように、与えられた自然環境を最大限に生かし、人々のうるおいある暮らしと農業をはじめとした産業・文化の調和を考え、魅力ある郷土作りと協同組合運動の実践に取り組んでおります。

【奥能登の"あえのこと"とは】
12月5日に苗代田から田の神を迎えて、当主みずからの采配により、目に見えない神を実際いますがごとく接待して、豊作に感謝する行事です。田の神は、そのまま家で越年すると信じられ、2月9日には再び12月と同様の儀礼をして豊年を祈り、田の神を送しだします。国の重要無形文化財に指定され、平成21年9月には、県内最初のユネスコ無形文化遺産に選定されました。「アエ」は田の神を供応する「饗」、「コト」はハレの行事を意味する「事」で、「饗の事」と考えられています。

【珠洲について】
すずの由来については、いくつかの説がありますが、ススは本来「稲」のことで、収穫祭に12個の小さな鈴を結った神楽鈴を振って報謝の舞を舞うが、シャンシャンと鳴らす鈴の音に由来するという説と養老2年(718年)越前国を割いて、羽咋、能登、鳳至、珠洲4郡からなる能登の国が立国し、天平20年(748年)大伴家持が能登を旅した折、都に残った妻を想って長歌を詠んでいるが、「珠洲の海士が潜って採っているという真珠を500個ばかり手に入れることができないものだろうか、都で私のことを想っている貴女に贈ってあげたいのに・・・」というもので、真珠のように美しい輝きを持つ美しい洲(くに)が家持の郡名に抱いた思いだったという説があります。


【おいしさの秘密】
土地と水と四季と、そしてねばり強い石川人気質
◇霊峰白山が育む清冽な水
◇「能登はやさしや土までも」と言い伝えられる肥沃な大地
◇土壌を豊かにしてくれる厳しく雪深い冬
◇稲を力強く育ててくれる陽の光ふりそそぐ暑い夏
◇ねばり強く根気のある石川県人気質
石川県は、美味しいお米のできる条件がそろっており、江戸時代より「加賀百万石」こめどころとして名をはせ、全国的にも知名度は高く、良質米生産県として評価されています。
【日本初の世界農業遺産に認定】
2011年(平成23年)6月、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町に広がる「能登の里山里海」が、新潟県佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」とともに、日本では初めて世界農業遺産に認定されました。

【世界農業遺産】
世界農業遺産(Globally Important Agricultural Heritage Systems(GIAHS):ジアス)は、2002年(平成14年)、食料の安定確保を目指す国際組織「国際連合食糧農業機関」(FAO、本部:イタリア・ローマ)によって開始されたプロジェクトです。
創設の背景には、近代農業の行き過ぎた生産性への偏重が、世界各地で森林破壊や水質汚染等の環境問題を引き起こし、さらには地域固有の文化や景観、生物多様性などの消失を招いてきたことが挙げられます。
世界農業遺産の目的は、近代化の中で失われつつあるその土地の環境を生かした伝統的な農業・農法、生物多様性が守られた土地利用、農村文化・農村景観などを「地域システム」として一体的に維持保全し、次世代へ継承していくことです。
国際連合教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))が推進する世界遺産が、遺跡や歴史的建造物、自然など「不動産」を登録し保護することを目的としているのに対して、世界農業遺産は、地域のシステムを認定することで保全につなげていくことを目指しています。

【世界農業遺産に認定までの経緯】
能登は、地域に根差した里山里海が集約された地域であり、今回の「能登の里山里海」の認定は、その総合力が評価されたものです。能登の農林水産業とそれに関連した人々の営みのすべてが「世界農業遺産」として認定されたのです。また、2010年(平成22年)10月、愛知県名古屋市で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」において、「SATOYAMAイニシアティブ」の推進が採択されるなど、近年の里山(SATOYAMA)に関する国際社会の関心の高まりも今回の認定の背景として挙げられます。
【里山とは】
里山は、集落、農地、それらを取り巻く二次林、人工林、採草地、竹林、ため池などがモザイク状に組み合わさって形成され、人が適度に利用することで、豊かな自然が形成・維持されてきた地域です。里山は、人の生活・生産活動の場であると同時に、多様な生きものの生息・生育空間ともなり、さらには地域固有の文化や景観も育むなど多様な価値を併せ持っています。

【里海とは】
人が様々な海の恵みを得ながら生活するなど、人の暮らしと深い関わりを持つ沿岸域を里海と呼びます。里海は生産性が高く豊かな生態系を持ち、魚類の産卵場所や稚魚の生育場所など、海の生きものにとっても重要な場所能登半島の地形は、低山と丘陵地が多いことが特徴です。また、三方を海に囲まれているため、遠浅の砂浜海岸や外浦と呼ばれる岩礁海岸、内浦と呼ばれるリアス式海岸を含む内湾性の海域と、海岸線も変化に富んでいます。日本海側気候型に属し、冬季には積雪がありますが、沖合を対馬暖流が流れているため、同緯度の他地域に比べて比較的温暖です。そのため、暖寒両系の動植物が生息する等、豊かな生物相が見られます。能登半島は、土地利用、農林水産業、食文化、祭礼、工芸、生物多様性などにおいて、里山から里海までが密接につながり、一体不可分となっている地域です。